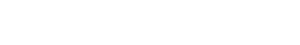金融緩和って何?
金融緩和にはどんなメリット・デメリットがあるの?
金融緩和と日本銀行の関係は?
こんな風に考えている人に向けて、この記事では解説しています。
金融緩和について分かりやすく知りたいと思っている人には、特におすすめの記事になっています。
スポンサーリンク
金融緩和とは

金融緩和とは日本銀行(中央銀行)が景気をよくするために、実施する金融政策を指します。
金融緩和の目的は、社会に出回る通貨の量を増やして、企業や個人がお金を使いやすくすることです。
世の中に出回るお金が増えれば景気が良くなり、「お金を積極的に使おう」を考える人が増えます。
金融緩和の内容は経済状況によって異なりますが、代表的なのは以下の政策です。
・お金を貸し出す際の金利を下げる
・国債を買い上げお金を市場に流す
金利が0%に近くこれ以上金利を下げられない現在では、国債を買い上げる手法が主に使われています。
ここからは金融緩和の詳しい内容や、量的緩和、質的緩和について解説していきます。
1つ上へ
関連
金融緩和の金利について
以前金融緩和政策として使われていた手法が、金利の引き下げです。
お金を貸し借りする際に発生する金利を下げることで、企業や個人は銀行などの金融機関からお金を借りやすくなります。
お金を借りやすくすれば、家や車を買ったり、新しく投資を行う人が増えて景気が改善すると以前は考えられていました。
しかし現在は金融緩和のため限界まで金利が下がってしまい、金利が0%に近い状態となるケースも出てきました。
金利が0%になれば、日本銀行はそれ以上金利を下げられません。
景気が良くないと感じている人が多い今、政府がどのような方法で景気を改善していくのかが注目されます。
-

-
【金融とは何か】金融の意味を分かりやすく解説
量的緩和・質的緩和
量的・質的緩和とは2013年に導入された金融緩和の強化策です。
量的・質的金融緩和の内容は、以下の通りとなっています。
・これまで以上に国債を購入する
・上場投資信託などの金融資産を購入する
それまで景気向上に向け、様々な政策を行ってきた日本銀行。
今回実施された量的・質的金融緩和では、単に通貨の量を増やすだけでなく買い上げる金融資産の質や内容についても見直されました。
この量的・質的緩和ではこれまで以上に世の中に出回るお金の量を増やし、物価を2%上昇させることを目的としています。
2%の物価上昇はまだ実現されていませんので、今後日本銀行が目標に向けどのような政策を実施するのか重要になります。
スポンサーリンク
金融緩和のメリット・デメリット

景気を良くするため実施されている金融緩和ですが、金融緩和を行えば日本経済全体が必ず明るくなる訳ではありません。
ここからは金融緩和のメリットとデメリットを解説していくので、金融や経済について理解を深めたい人はぜひチェックしてください。
金融緩和のメリット
本来の目的通り、金融緩和のメリットは景気回復にあります。
金融緩和を行い、通貨の供給量が増えれば物価が上がり、企業の業績や給料もアップします。
金利が下がりお金が借りやすくなる上、給料がアップすれば「お金を使おう」と考える人が増え好景気になるでしょう。
金融緩和が上手く行けばお金の動きが活発になるため、経済停滞を引き起こすデフレから脱却できるのです。
金融緩和のデメリット
しかし金融緩和を行ったからと言って、必ず景気が回復する訳ではありません。
金融緩和にもデメリットは存在します。
金融緩和を行って効果がないだけなら良いのですが、物価が上がったものの給料はアップしない状況になれば、家計が苦しくなることも考えられます。
金融緩和を行っても「景気が回復した」実感を持っていなければ、お金を積極的に使う人は減ってしまうでしょう。
-

-
家計とは何か|家計金融資産や家計消費から分かりやすく解説
金融緩和による円安・円高
金融緩和で金利が下がれば、社会全体に出回る通貨の量が増えます。
そして通貨の量が増えると円の価値が下がり、海外の通貨と比べ円が安い状態になるのです。
円安になると、日本の製品を安く輸出できるため海外の人に購入してもらいやすくなります。
輸出で大きな利益を得ている車関連のメーカーなどにとって、円安は非常に有難いことです。
反対に円の価値が下がると海外製品の値段が上がってしまうため、海外からものを輸入して加工・販売する企業の利益は減ります。
金融緩和による円安の恩恵を受けられるかどうかは、企業が行う事業の内容によって異なるのです。
スポンサーリンク
金融緩和における日本銀行の役割

日本銀行(中央銀行)は政府主導のもと、金融緩和を実施する立場にあります。
もともと日本銀行は、紙幣を発行したり国民から集めた税金を管理したりできる特別な銀行です。
物価を安定させ、日本経済全体を発展させる本来の役割を果たすため、日本銀行は積極的に金融緩和を行っているのです。
-

-
中央銀行とは?わかりやすく解説|3つの役割について
異次元緩和
異次元緩和とは日銀の黒田総裁が2013年にスタートした金融緩和政策です。
先ほど説明した「量的・質的緩和」と同じ政策を指しますが、「異次元緩和」の方が一般的な呼び方として良く知られています。
もともと異次元緩和は「かつてない異次元レベルの緩和」という意味で使われた言葉です。
日銀が市場に投入するお金の量を2倍にして、大幅に通貨供給量を上げる内容でしたが、現在まで物価上昇率2%アップという目標は達成されていません。
金融機関が日本銀行にお金を預ける際の金利を0%以下にする「マイナス金利政策」も実施されましたが、目標実現にはまだ時間がかかると考えられています。
まとめ
金融緩和とは・金融緩和のメリット/デメリット・金融緩和における日本銀行の役割などについて解説してきました!
ニュースで頻繁に登場する金融緩和が理解できれば、国内経済だけなく世界の経済についても理解しやすくなります。
物価上昇や景気回復のため、これからも日銀は金融緩和政策を続けていくはずです。
積極的に情報収集を行い、景気についてしっかりアンテナを張っておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました(*'▽')